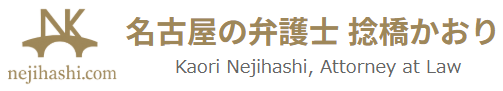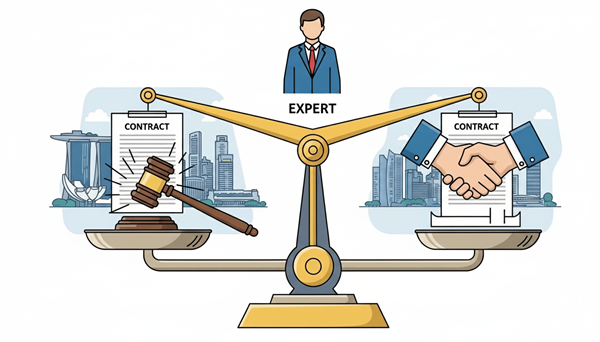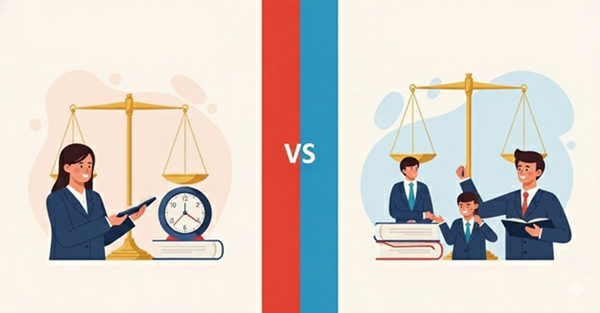前記事で、国際取引紛争解決における仲裁と調停の違いや、その併用についての総論を書きました。
本記事では、シンガポールを例に具体的に見てみたいと思います。なぜシンガポールかと言うと、シンガポールは国際紛争解決の中心地となることを目指して、積極的に法制度や組織の整備を進めているためです。
利用実績も多く、日本企業が国際取引に際して仲裁機関を選ぶ場合、特に相手がアジアの企業である場合は、シンガポール国際仲裁センターが、(最)上位の選択肢になることが多いのではないかと思います。
シンガポールにおける仲裁と調停の併用の仕組み
仲裁センターと調停センターの協定書の概要
シンガポールでは、仲裁機関と調停機関が分かれており、
仲裁機関は、シンガポール国際仲裁センター(Singapore International Arbitration Centre)(SIAC)
調停機関は、シンガポール国際調停センター(Singapore International Mediation Centre)(SIMC)です。
両者は別組織ですが、協定(SIAC-SIMC Arb-Med-Arb議定書)が結ばれていて、利用者が併用しやすいようになっています。議定書によると、併用する場合には、大枠として以下の手順で進みます。
② 相手方(被申立人)はSIACに答弁書を出し、この時点で、仲裁人は仲裁手続を中断する。
③ SIACの事務局が事件記録をSIMCに送り、SIMCにおいて調停人を選任の上で調停を行う。調停は原則として8週間以内で終える。
④ 調停において紛争の全部または一部が解決できなかった場合は、未解決の部分について、SIACにおいて仲裁手続を再開する。
⑤ 調停において和解が成立し、当事者の希望がある場合には、SIACにおける仲裁人は、当事者が合意した内容に沿った仲裁判断を出すことができる。
調停で合意した内容に沿って仲裁判断を出す理由
調停で和解が成立した場合、当事者間で単純に和解合意書にサインしてもよいのですが、上記⑤のように、合意内容に沿った仲裁判断を出せるようになっているのは、合意内容を仲裁判断の形にして貰うことにより、前記事に書いたニューヨーク条約に基づく強制執行ができるようになるからです。
和解が成立した場合、双方が納得して和解している訳ですから、和解内容が履行される(例えば、和解金としていくら支払うと約束したら、その通りに支払われる)ことが多いと言われていますが、いったん払うと約束しておきながら、その約束を反故にされる可能性もゼロではありません。
その場合、単純な和解合意書しかないと、それだけでは強制執行することができず、改めて裁判なり仲裁なりを起こさなければならなくなります。そのような事態を避けるために、上記⑤のように和解内容に沿って仲裁判断を出して貰うことが望ましいです。
調停に関するシンガポール条約について
もっとも、今月(2020年9月)、「調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約」が発効しました。シンガポールが旗振り役になったため、通称として「調停に関するシンガポール条約」、あるいは単に「シンガポール条約」と呼ばれることもあります。
これは国際的な調停を経て和解合意に至った場合、(仲裁判断がなくても)和解合意書だけで強制執行できるようにしようという条約です。
日本は現時点で未加盟ですが、日本企業がこれを利用できる場合もあります(加盟国に相手の資産がある場合)ので、この条約についてはまた改めて書きたいと思います。[その後日本が加盟しましたので、末尾に追記があります]
公表されているモデル条項
SIAC及びSIMCのサイトでは、契約書における定め方の例として、以下のモデル条項が掲載されています。
紛争を仲裁で解決することの合意(仲裁合意)
まずは紛争を仲裁で解決することに合意する文言です。少なくとも、ここまでは事前に合意しておく必要があります。
紛争が始まってから仲裁合意をすることも法律上は可能ですが、前記事で書いたとおり、紛争が始まってから仲裁合意をすることは実際は難しいことが多いです。
The seat of the arbitration shall be [Singapore].*
The Tribunal shall consist of _________________** arbitrator(s).
The language of the arbitration shall be ________________.
The law governing this arbitration agreement shall be _________.
仲裁手続の途中で調停を誠実に試みることの合意
ここから先は、仲裁手続の途中で調停を試みることの合意です。仲裁の開始後に、SIMCにおける調停により紛争を解決できるよう「誠実に」試みること、また調停により和解が成立した場合には、SIACに戻って和解した内容に沿って仲裁判断を出して貰う、ということが書かれています。
調停を利用することについて、必ずしも契約書に定めておく必要はなく、その時点で合意することもできますが、紛争を話し合いで解決できるよう「誠実に」試みる、ということを契約書で定めておくことにも意味があるように思います。
また、上記のようにどこの調停機関を使うかということまで具体的に書いておくのが望ましいと思います。
2025年10月追記:日本のシンガポール条約加盟について
その後、日本はシンガポール条約に加盟し、同条約は2024年4月1日から日本において効力を生じています。
現時点での加盟国は18か国です(最新の加盟状況はこちらで確認できます)。
シンガポール条約は相互主義を採用していないため、仮に相手企業の所在国が加盟していなくても、日本など加盟国においては調停による和解合意を執行できる可能性があります。その一方で、相手国が非加盟国であれば、その国では執行できない点に注意が必要です。
もっとも、日本は条約の適用を「オプトイン方式(opt-in)」で採用しています。そのため、和解合意の当事者間で「この和解をシンガポール条約に基づき強制執行可能とする」との明示的な合意がなければ、日本国内で強制執行することはできません。
日本企業としては、国際調停による和解を行う際、相手企業の国(または相手企業が資産を有する国)が加盟国か否かを確認しつつ、オプトイン条項を設けるかどうかを慎重に検討する必要があります。
これは執行可能性に直結する重要な法的判断を伴いますので、実際の和解条項の作成にあたっては必ず弁護士にご相談ください。