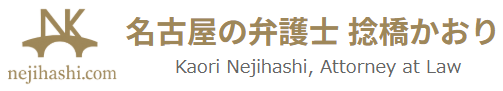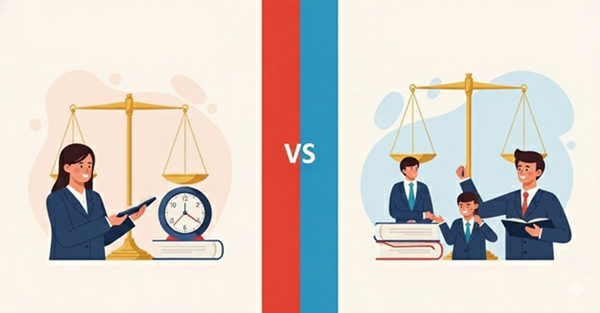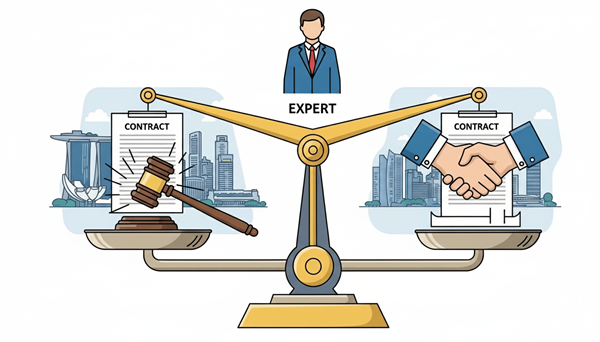国際取引紛争の解決に関して、「仲裁」や「調停」という話がされることが多いですが、両者は法的に全く違うものです。
ただ、最近は、それぞれの性質を生かしながら、うまく組み合わせて使おうという動きが進んでいます。本記事では、仲裁と調停の違いや、その併用についての総論を書きたいと思います。
次の記事で、シンガポールを例に、具体的な併用の仕組み(取扱機関の間の取決めの内容)や、公表されているモデル条項について書きたいと思いますので、総論は大丈夫という方は、次の記事に飛んで頂ければと思います。
「仲裁」(Arbitration)とは
裁判官に代わる仲裁人による判断
「仲裁」(Arbitration)」とは、紛争の当事者の合意により、どこかの国の裁判所ではなく、当事者が選んだ仲裁人に判断を委ね、その判断に従う、という制度です。
当事者がいったん紛争を仲裁に付すことについて合意すれば、仲裁人は紛争について判断する権限を有し、一方当事者に対して、一定金額の支払いを命じたりすることができます。
仲裁判断に従わなければ強制執行をすることができる(ニューヨーク条約加盟国)
支払いを命じられた当事者が仲裁人の判断に従わない場合には、勝った当事者は負けた当事者の資産に対して、強制執行(差押え等)をすることができます。
強制執行ができるのは、ニューヨーク条約(外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約)という世界で150ヶ国以上が加盟する条約があり、その加盟国においては、外国における仲裁判断を(条約に定められた例外的な事由に当たらない限り)強制執行ができる仕組みがあるためです。
このような条約に基づく強制執行の仕組みは、裁判所の判決にはないものです。
仲裁のその他のメリット
このような執行面での利点に加え、
- 第三者に紛争の内容を知られない(裁判のように公開の法廷で行われない)
- 一審制である(上訴の仕組みがない)
- 両当事者と違う国籍の人を仲裁人とすることにより公平性を図れる
などのメリットがあるため、国際取引においては、裁判に代わる紛争解決方法として、予め契約書において仲裁合意(紛争になった場合には仲裁で解決するという合意)がなされることが多いです。
コストの問題
このように多くのメリットがある仲裁ですが、一番の問題はコストだと思います。弁護士費用に加え、仲裁機関の手数料や仲裁人の報酬も当事者負担となりますので、特に中小規模の企業にとっては、コスト面で負担を感じることが多いです。
(もっとも、各仲裁機関において、紛争となっている金額に応じてコストを下げるよう努力をされています。各機関における迅速仲裁(簡易仲裁)の仕組みについては、こちらの記事をご参照下さい)
「調停」(Mediation)とは
仲裁におけるコスト面での負担や、やはり話し合いによる解決が望ましいという観点から、国際取引紛争を「調停」で解決しようという動きがあります。
「調停」とは、調停人のあっせんの下で、当事者間の合意(和解)により紛争を解決しようというものです。調停人の役割は、話し合いによる合意形成を促進することですが、最終的に和解が成立するためには当事者双方の同意が必要です。
調停人がいかに素晴らしい和解案を持っていても、当事者に和解を強制することはできません。この点が、仲裁人が強制的に判断を下すことができる仲裁と決定的に違います。
仲裁と調停の併用
このように仲裁と調停は法的に全く違うものですが、両者の性質を生かしながら、うまく組み合わせて使おうというのが、最近の動きです。
基本的には、予め契約書において、仲裁合意をしておきます。いったん紛争が始まると、どこで解決するかということすら合意できない場合が多いので、最初に、万一紛争になったら(どこどこの仲裁機関による)仲裁で解決する、ということを合意しておく必要があるからです。
実際に紛争が発生したら、まず仲裁合意に基づいて仲裁手続の申立てをした上で、仲裁手続を早い段階で中断して、調停に移行し、第三者である調停人を交えて、話し合いによる解決ができないかを試みます。
上記のとおり、調停では当事者に和解を強制することはできませんが、早期解決を望む側の当事者としては、最初に仲裁手続を申し立てておくことで、和解できない場合にはすぐに仲裁手続に戻って仲裁人に判断を下して貰えるという利点があります。
仲裁人と調停人は同じ人か別の人か
2025年10月追記。日本の企業から、また弁護士からも質問が多い内容のため、追記しました。
別の人であることが原則
仲裁と調停を併用する場合、仲裁人と調停人は同じ人が務めるのでしょうか?それとも別の人が務めるのでしょうか?
世界の標準は、「別の人」です。
(日本の裁判中の和解協議は例外)
日本では、裁判の途中で、和解の話し合いが行われることが多く、その時には、それまで審理を担当してきて最終的に判決を下すことになる裁判官が、和解を主導します。それぞれの当事者が別々に裁判官と話をして、考えていることや、どのくらいの金額なら和解できるというような話をします。
世界的に見ると、これはやや特殊な運用と受け取られます。たとえば被告側の弁護士が「●●円くらいなら払って和解してもよい」と述べた場合、仮に和解が成立せずに裁判官が判決を下す際に、「被告は●●円くらい払うと言っていたな…」ということが裁判官の心に影響を与えるのではないか、というのが欧米の考え方だからです。「原告が●●円貰えれば和解してもよいと言っていたな…」ということも同様です。
日本では伝統的に裁判官への信頼が厚く、「裁判官は和解協議での話し合いに影響を受けずに。仮に和解が成立しなかったら改めて法的判断を行って判決を下すはずだ」との信頼があるからこそ、裁判官の主導による和解協議が成り立っています。もっとも、裁判官も人間ですから、深層心理で影響を受ける可能性があることは否定しきれず、弁護士としては100%の本音を話すことは躊躇するようなケースもあります。
国際仲裁での取り扱い
上記のような理由で、国際仲裁では、仲裁人と調停人は別の人になることが原則です。例えば、仲裁手続の途中で、和解できないか調停を試みてみましょうとなった場合、仲裁人とは別の人を調停人に選びます。
するとその人は全く案件の中身を知らない人ですから、改めてゼロから事案を説明して知って貰った上で、調停をして貰う必要があることになります。
裁判官による和解協議に慣れた日本人にとっては、これが二重のコストに感じられることがあります。そして実際、世界で活躍する調停人の時間当たりの単価はとても高いです。
ただ、私も何度か高名な調停人の講演などを聞いたことがありますが、彼らは本当に調停のプロです。調停人の活動だけで生計を立てている人も少なくなく、調停人としての訓練と経験を積んでいます。ビジネス紛争は基本的には話し合いで解決(金銭的合意で解決)できる性質ものが多いと思いますので、もちろん案件次第ですが、仲裁人とは異なる調停人に入って貰って和解を試みる価値がある場面もあるだろうと思います。
逆に、日本の裁判と同じ感覚で、「和解したいなぁ。仲裁人から和解の話を出してくれないかなぁ」と内心で思っていても、それは仲裁人の役割ではないので、仲裁人の方からそのような話が出されることは基本的にないのではと思います。
日本商事仲裁協会(JCAA)の場合
日本商事仲裁協会の商事仲裁規則においても、以下のとおり、仲裁人とは異なる者を調停人とすることが原則であるとされています。
1 当事者は、 いつでも、 書面による合意により、 仲裁事件に係る紛争をJCAAの商事調停規則に基づく調停手続に付することができる。 この場合には、 次条第1項の場合を除き、 当該紛争を担当している仲裁人とは異なる者を調停人に選任するものとする。
もっとも、両当事者の合意がある場合には、仲裁人を調停人とすることができるとの例外措置があります。
他の仲裁機関の規則にこのような例外的措置が組み込まれているかどうかは確認できていませんが、特に中小規模の日本の企業にとっては、この例外的措置により仲裁人にそのまま調停人を務めて貰いたいと感じることもあるのではないかと思います。
相手の同意も必要なことなので、一方当事者の一存でそうすることはできません。ただし、相手企業によっては、最終的な判断権を有する人が途中で和解の斡旋を行うことに、あまり抵抗を感じない場合もあります。相手企業の国の文化や法的慣習にも左右されるでしょう。
上記のように、国際仲裁では、仲裁人と調停人を分けることによって、公正性と中立性を確保する考え方が一般的です。もっとも、仲裁規則が許容する場合には、当事者間の信頼関係や案件の性質によって、例外規定の活用を検討する余地もあります。