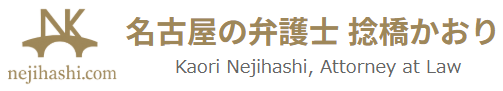はじめに
しばらく投稿がない期間が続いてしまいました。日々の業務に忙殺されていましたが、中でも1-2ヶ月集中的に取り組んでいた案件である、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」(ハーグ条約)に基づく子の返還申立について書きたいと思います。
ハーグ条約に基づく子の返還申立は、子供に関するものですので、家庭裁判所が取り扱う家事事件に属します。私は元々ビジネスの分野を取り扱ってきましたが、2013年頃からは国際家事事件も取り扱っています。
「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」(ハーグ条約)とは
趣旨
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」(ハーグ条約)は、国家間の条約です。1980年に採択され、日本は長く加盟していませんでしたが、2014年に加盟しました。2021年11月時点の加盟国は101カ国です。
この条約が採択された背景としては、国際結婚や国際的な転居が増える中、ある日突然、一方の親(Taking Parent(TP)と呼ばれます)が他方の親(Left Behind Parent(LBP)と呼ばれます)に無断で子供を連れて母国などに帰国してしまう、あるいは子供を連れて母国などに一時的に帰国したはずが元の国に戻ってこないという問題が多く発生したためです。
そこで、国家間の取り決めとして、このような場合にはまずは子供を元の国に戻して、両親の間で争いがあるのであれば、子供が元々住んでいたの国の裁判所が子供の監護について判断できるようにしようということで、この条約が採択されました。
申立先は連れて行かれた先の国の裁判所
ハーグ条約は国と国の間の条約ですので、締約国に義務を負わせるものです。締約国は、条約に沿った国内法を整備する義務を負います。日本では、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律」(ハーグ条約実施法)という国内法が制定されています。
日本に連れてこられた子供について法的手続を取る際には、この国内法に基づき、日本の裁判所で手続を取ることになります。
日本の場合、東京家庭裁判所と大阪家庭裁判所の専属管轄となっており、子供が東日本にいる場合(子の住所地が東京高裁、名古屋高裁、仙台高裁または札幌高裁の管轄区域内にある場合)は東京家庭裁判所、子供が西日本にいる場合(子の住所地が大阪高裁、広島高裁、福岡高裁または高松高裁の管轄区域内にある場合)は大阪家庭裁判所となります。
外国に取り残された親(LBP)としては、子供が日本のどこにいるか分からない場合も多いですが、この場合は住所不明のままの状態で基本的に東京家庭裁判所に申し立てします。
下記のとおりハーグ条約案件では外務省の支援が受けられることが多く、外務省は調査を通じて子供と一緒にいる親の所在を把握しています。住所不明のまま申立てを受けた裁判所は、外務省に照会をして所在を把握し、子供と一緒にいる親に対して、申立書や呼出状などの書類を送達します。
裁判所は、原則として申立があってから6週間以内に、子供を元の国に返すかどうかの結論を出すことが求められています。
裁判では常居所地国への返還が原則
上記のような趣旨で採択されたハーグ条約ですので、原則は子供を元々住んでいた国に戻すことになります。元々住んでいた国に戻した上で、両親の間で子の監護(どこに住むかを含む)について争いがあれば、その国の裁判所で判断しようというのが基本的な考え方です。
ただ、中には、元の国に返すとどうしても危険だというような場合や、ある程度大きい子供がはっきりと帰りたくないと言っているような場合もありますので、一定の例外事由に該当する場合には、返さないという判断がなされることになります。どのような場合に返さないという判断ができるかについても、条約で決められています。
「元々住んでいた国」「元の国」という書き方をしましたが、法律の言葉としては「常居所地国」に返すこととされています。そして実は、「常居所地国」がどこかを巡って争いになることがかなり多いです。外国に取り残された親(LBP)が日本の裁判所に対してハーグ条約に基づく返還を申し立てたところ、子供と一緒に日本にいる親(TP)から、常居所地国は日本であるという主張が出される場合です。(事案ごとの判断になりますので、具体的な案件については弁護士にご相談下さい。)
外務省の援助
ハーグ条約に基づく案件の特色として、外務省の援助が受けられるということがあります。全ての案件で援助が受けられる訳ではなく、一定の条件を満たす必要がありますが、多くのハーグ条約案件において援助を受けることができます。
外務省の援助の内容については、外務省のハーグ条約に関するサイトで詳しく説明されていますが、裁判所外のあっせん機関を利用する場合のその負担、裁判の際の翻訳支援、面会交流支援などです。
裁判との絡みでは、翻訳支援を受けられるのがとても大きいです。外国で暮らしていた子供が日本に連れてこられた訳ですので、証拠資料が外国語であることが多いです。両親の間のコミュニケーション(メールやLINEの記録)が証拠とされることも多いですが、これも外国語であることが多いです。
一方で申立先は日本の裁判所ですので、証拠を提出する際には全て日本語訳を付ける必要があり、これを自費で手配しようとすると膨大な費用になります。上限設定はあるようですが、外務省の援助(費用負担)で、かなりの分量の翻訳を迅速に手配して貰えますので、大変助かります。
話し合いによる解決の試み
ハーグ条約では、話し合いによる解決が望ましいと考えられており、裁判所外のあっせん機関での話し合いのための制度も整えられています。具体的には、外務省から、全国の複数のあっせん機関との間で委託契約が締結されており、これらのあっせん機関を利用する際の利用料は外務省が負担することとなっています。
また、裁判所への申立て後も、審理と並行して調停が行われ、調停期日が集中して設けられます。通常の家事調停は1〜2ヶ月に一度くらいしか期日がありませんが、ハーグ条約の場合、上記のとおり裁判所は申立から6週間以内に結論を出さなければなりませんので、6週間の枠組みの中で調停も行われます。

上記のとおりハーグ条約は、子供を常居所地国に返還することを趣旨とする条約で、その先の監護については踏み込まない、それは常居所地国の裁判所が判断するという建て付けなのですが、あっせんや調停での話し合いでは、常居所地国に帰った後のことについても話し合います。当事者や子供にとっては、帰ったその日から生活があるので、ある程度のことはは決めておいた方が望ましいためです。
ただ、帰った後のことについてどの程度の期間について、どの程度詳しく決めるかは事案ごとに異なります。当座の半年くらいのことについて決めておくのが、あるいは数年単位で決めるのか、もっと長いのかなどです。自分が返還を求める立場なのか、求められる立場なのかによっても、どこまで決めておきたいかが変わってくると思います。
雑感
上記のとおり、ハーグ条約に基づく返還申立の案件は、東京家庭裁判所と大阪家庭裁判所の専属管轄とされています。私は名古屋を拠点にしており、名古屋家庭裁判所には管轄はないのですが(面会交流案件については管轄があります)、ご縁があった案件(外国からの突然の問い合わせを含む)について、東京や大阪の裁判所に出張して対応しています。
前回は東京家庭裁判所でのTP側(返還を求められている側)の案件で、今回は大阪家庭裁判所のLBP側(返還を求める側)の案件でした。連日で期日が入ることもあり、しかも裁判所から翌日の期日に向けた宿題を出されることが多いので、夜に宿泊先のホテルで準備をすることになります。
この類型の案件は、上記の6週間以内という制約があるために集中的に対応する必要があり、また当事者間の対立(不仲というよりどの国で子供を育てたいかという希望の対立)が強いことが多いために、弁護士にとっても気力と体力と熱意が要求されるものです。
今回の案件が終わった時、依頼者からは、「ありがとう。大変だったでしょう?ハードワークしてくれたのは分かっている。もうハーグ条約案件はやりたくないんじゃない?」という言葉を頂きました。最後の言葉は思わず笑いましたが、ご縁があれば引き続き取り扱っていきたいと思っています。