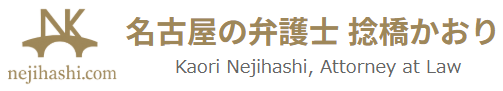前記事で、国際売買取引を始める際に把握しておくべきポイントを、4つ、挙げました。
今回はその1つ目、「裁判管轄条項か仲裁条項か(日本の裁判所ではなぜ問題か)」について詳しく書きたいと思います。
いったん理屈を理解してしまえば、覚えやすいところでもあると思いますので、理屈から書きたいと思いますが、理屈はあんまり、、、という方は、「実務的な対応」まで飛んで頂いても大丈夫です。
外国の裁判所の判決を日本に持ってきたら、どうなるか?
まず日本の法律の話から始めたいと思います。
アメリカの会社X社が、日本の会社Y社をアメリカの裁判所で訴え、勝訴判決を得たとします。しかし、Y社は判決を無視して支払いません。Y社の財産は日本にしかありません。
X社は、アメリカの裁判所の判決に基づき、日本にあるY社の資産に対して強制執行(差押等)できるでしょうか?
これについて定めているのは、民事執行法です。条文は読み飛ばして頂いても大丈夫ですが、
22条 強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
6号 確定した執行判決のある外国裁判所の判決(…省略…)
(外国裁判所の判決の執行判決)
24条 外国裁判所の判決についての執行判決を求める訴えは、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所(…省略…)が管轄し、この普通裁判籍がないときは、請求の目的又は差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
2 (省略)
3 (省略)
4 執行判決は、裁判の当否を調査しないでしなければならない。
5 第1項の訴えは、外国裁判所の判決が、確定したことが証明されないとき、又は民事訴訟法第118条各号(…省略…)に掲げる要件を具備しないときは、却下しなければならない。
6 執行判決においては、外国裁判所の判決による強制執行を許す旨を宣言しなければならない。
要は、外国裁判所の判決を日本に持ってきた場合、それが確定(外国の裁判所で上訴などができないこと)していて、日本の民事訴訟法118条の各号を満たす場合には、日本の裁判所が執行判決を出し、それに基づき、強制執行できる、ということです。
では、民事訴訟法118条の規定はどうなっているのでしょうか?
118条 外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。
1 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。
2 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。
3 判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。
4 相互の保証があること。
上記の1号から4号の要件については、繰り返し判例で争われており、解説しようと思うと本の一章が書けてしまいますので、割愛させて頂きますが、
ポイントとしては、外国裁判所の判決に基づき、日本の財産に対して強制執行できるかどうかは、日本の法律で決まる、ということです。
日本の裁判所の判決を外国に持って行ったら、どうなるか?
では、逆のパターン、すなわち、日本の裁判所の判決を外国に持って行ったら、どうでしょうか?それに基づき強制執行して貰えるでしょうか?
答えは、その国の法律により決まる、です。
代表的な国の例を挙げると、一般的に以下のように理解されています。
中国
中国においては、経済的な事案に関する日本の裁判所の判決に基づき、強制執行することはできません。(なお、逆もまた同様で、経済取引に関する中国の裁判所の判決に基づき、日本で強制執行することはできません。)
ドイツ
ドイツにおいては、ドイツの民事訴訟法328条が定める5つの要件を満たせば、外国の裁判所の判決に基づく強制執行ができることになっています。
ドイツの民事訴訟法328条の5つの要件というのは、上記の日本の民事訴訟法118条の4つの要件と極めて似ています。(日本は4つなのに対してドイツは5つですが、内容的には、日本の4つのうちの1つで、ドイツの2つをカバーしています。)
日本の民事訴訟法118条4号の「相互の保証があること」というのは、相手国においても類似の要件の下で日本の裁判所の判決に基づく強制執行ができるということですが、日本とドイツの間では、相互保証があると考えられています。
なお、ドイツの民事訴訟法の英訳版は、こちらで見れます。
イギリス、アメリカなど
イギリスやアメリカ、オーストラリアなどの英米法の国では、判例法(コモンロー)の考え方として、一定の要件を満たす場合に、一定の手続を踏んだ上で、外国裁判所の判決に基づく強制執行を認めるという考え方があります。
具体的な要件の詳細は国(アメリカの場合は州)によって微妙に違いますが、大きくは、判決を下した外国裁判所が管轄権を有していたこと、確定した金額の支払いを命ずる判決であること、詐欺により得られた判決でないこと、自国の公序に反しないこと、などです。外国裁判所の審理に被告が出頭しなかった場合をどう考えるかについては、国により違いがあるようです。
日本では、一般論としては、イギリス、シンガポール、オーストラリア、アメリカのニューヨーク州やカリフォルニア州などとの間では、相互保証があると考えられています。(個々の案件については、慎重な検討が必要です。)
実務的な対応
上記のように、日本の裁判所の(経済的な事案の)判決を中国に持って行ってもダメなことははっきりしていますが、国によっては、日本の裁判所の判決に基づき、強制執行して貰える可能性はあります。
しかし、あくまで外国の法律に基づく、外国の裁判所での運用ですので、本当に強制執行して貰えるのか、どうしても不確実性が残ります。
基本的には、どの国においても、外国裁判所の判決に基づく強制執行に対しては、何だかんだと主張して争われる可能性が高いのではないかと思います。(敗訴した当事者が判決に従って任意に支払えば、そもそも強制執行の問題にならないので、強制執行が必要になるということは、敗訴した当事者が判決に従った支払いを拒否している状況です。)
前置きが長くなりましたが、、、このような背景があり、国際取引においては、一般的に裁判所での裁判に代わり、仲裁による紛争解決が選択されます。(「被告地の裁判所」「被告地主義」という選択肢については後述します。)
仲裁とは?
仲裁とは、以前の記事に詳しく書いていますが、当事者の合意により、どこかの国の裁判所ではなく、当事者が選んだ仲裁人に判断を委ね、その判断に従う、という制度です。
仲裁人が下した判断については、万一負けた当事者が従わなくても、ニューヨーク条約に基づき、(条約に定められた例外的な事由に当たらない限り)強制執行できます。
ただ、上記のカッコ書きのとおり、ニューヨーク条約にも、例外的な事由(加盟国が強制執行を認めなくてもよい事由)が定められていて、その事由を広く解釈するか、狭く解釈するかについては、加盟国ごとに変わり得ます。
典型的には、ある仲裁判断に基づく強制執行を認めることが加盟国の「公の秩序に反する場合」には、強制執行を認めなくてもよいとされているため、発展途上国では「公の秩序に反する場合」が広く解釈されがちであると言われています。
もっとも、各加盟国における運用状況については、他の加盟国も調査したり統計を取ったりしていますので、国際社会の中であまり無茶なことはできないという抑止力がある程度は働いているものと思いますし、他にこれ(ニューヨーク条約に基づく強制執行)以上に確実と言える選択肢がないのが現実だと思います。
仲裁と調停の併用
また、これも以前の記事に書いていますが、ここ数年、仲裁と調停(話し合いによる解決を試みる制度)の併用を促進しようという動きがあります。
典型的には、まず仲裁を申し立てた上で、早い段階で調停に回し、調停の話し合いで解決できればその内容のとおりの仲裁判断を出して貰う、話し合いで解決できなければ仲裁に戻って仲裁人に判断を出して貰う、という仕組みです。
被告地の裁判所という選択(被告地主義)
一方で、仲裁とは別の選択肢として、被告地の裁判所、という選択肢もあります。
いわゆる「被告地主義」と呼ばれるもので、日本企業の方から相手を訴える場合には相手の国の裁判所で訴え、相手の方から日本企業を訴える場合には日本の裁判所(具合的な地方裁判所を指定します)で訴える、ということを契約書で合意することです。
これは、一見公平そうに見えるため、管轄条項で揉めた場合に、落としどころとしやすいです。また、被告(訴えられる側)の国の裁判所が判決を出しますので、原告(訴える側)が勝てば、その判決に基づいて、その国にある被告の財産に対して強制執行をすることができます。
ただ、実際には必ずしも公平とは限りません。
なぜなら、取引の構造や条件などによって、自分と相手の、どちらが原告になりやすいか(=自ら回収に動かなければならない事態に陥りやすいか)が決まり、原告になりやすい当事者にとっては、被告地主義は不利な取り決めとも言えるからです。(上記のとおり、勝てば強制執行しやすいというメリットもありますが。)
逆に、以下のような場合であれば、被告地主義は、自社にとって良い取り決めであると言えると思います。
(1) 自分の方から回収に動かなければならない事態となる可能性が低いこと
典型的には、単純な売買取引で、100%前払いで代金を受け取るという条件の場合、売主の方から訴えを起こす必要が生じる可能性は低いのではないかと思います。
(2) 万一自分から提訴しなければならない事態になっても、相手の国の裁判所がそれなりに利用しやすいこと
まとめ
以上、簡潔にしようと思いつつ、長くなってしまいましたが、国際取引においては、基本的には、仲裁合意をするか、もしくは、被告地主義を採用することが原則となります。
仲裁合意をする際には、併せて、まず調停を試みるという合意もしておくとよいと思います。以前の記事で、シンガポールを例にモデル条項を紹介していますが、他の仲裁機関や調停機関でも、モデル条項を公表しています。
関連記事:仲裁と調停の違いと、その併用について(シンガポールの具体例)
* 具体的な案件において何がベストかについては、企業規模や取引の構造・条件などを考慮して総合判断となりますので、こちらより、お問い合わせ下さい。